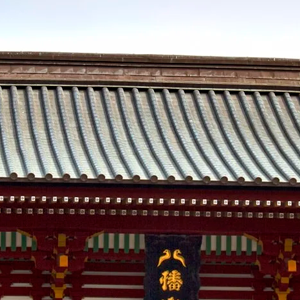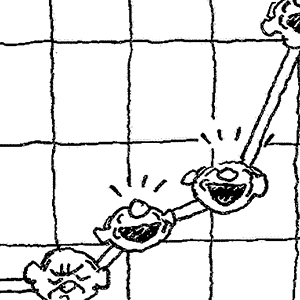武道、芸道における残心
「残心」とは、日本の武道や芸道で使われる言葉で「心を残す、心を途切れさせない」という意味である。私は学生時代から剣道を続けているのだが、残心があるかないかは有効打突(通称:一本)になるかならないかの運命の分かれ道となることを、身をもって感じている。
竹刀が打突部に正しく当たったとしても、残心がなければ無効とされ、これまで磨き上げた技術や努力が一本に至らない瞬間をたくさん見て、私自身も経験してきた。有効打突については、全日本剣道連盟の試合審判規則では下記の通りに定められている。
有効打突は、充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるものとする。(参照 [有効打突]第12条)
「残心」と言葉にすると、正直、非常に曖昧でわかりづらい。「残心あるもの」かどうかは、声の大きさ、時間の長さ、相手との距離などの明確な決まりはなく、その時々の状況によって判断がなされるのだが、稽古を重ねていくと、形なき残心を感じ取れるようになる。
目には見えない心
そもそも心は目には見えないものであることを考えれば、残心が重要で、その有無が致命的に結果に影響することを規則にしっかりと明記し、稽古などの実践の場を通じて人から人へと受け継がれている仕組みと精神性があることがとても大切であることに気付かされた。このことは、本号のテーマに通じることが充分にあると感じる。
2023年6月号のマーケティングホライズンでは「Simplify 削ぎ落としたら、何が残るのか」と題し、各分野で活躍される方々から“Simplify する先に何を見据えるか”、そして“何を未来に残したいか”を考える機会をいただいた。各人各様のありようから考えてみたい。
鎌倉の地で、「鳩サブレー」のブランドを築き上げられた豊島屋の久保田陽彦氏からは、「和の心」を教えていただいた。日本で知らない人がいないと言っても過言ではない鳩サブレーを作り、そして守る裏側には、主人と職人の絶え間ない言葉のキャッチボールがあった。
改めて“和”を調べてみると、複数ある意味の中に「二つの物事を一つに調和させる。また、混ぜ合わせて一つにする」(日本国語辞典)とあった。久保田氏は「『それ駄目だよ』って言ってくれるいろいろな声をきちんと聞いて、対話をしていかないといけませんね」とおっしゃられていたが、まさにネガティブな言葉も含めたいろいろな声を混ぜ合わせて一つにしていく作業が“言葉のキャッチボール”であり“和の心”なのだと感じた。
SAVANT 幾田桃子氏は、人種差別や環境汚染などの多くの社会問題に対して、ファッション、アート、さらには建築という手段で解決に向けて、経営者、デザイナー、そして社会活動家として実践する中で「トップサイクル」という考え方を導き出した。
それは、素晴らしい人間の脳で生み出された技術とデザインを活用し、ゴミをゴミとしてではなく、普通を超えてトップなものを創造することを指すが、「子どもも大人も、奇跡の存在です」とおっしゃられたことから、n=1という一人ひとりの人間自体が、普通を超えてトップな存在であることに気付かされた。
子どもも大人も、男性も女性も奇跡の存在で素晴らしい。そんな究極にシンプルなことを当たり前に言葉にできる環境だからこそ、自分の中にある言葉が自然と引き出され、心地よい対話が循環し、そこから新しい価値が生み出されるのだ。
そして政治家の市川房枝氏の思いを伝え広める活動として生まれた「38プロジェクト」に関しては、『女性展望』という雑誌、廃材で製作したブックスタンドがオフィスという一つの建築空間に集結することで生み出される“和”があると感じた。
これまでの建築の考え方は、スクラップアンドビルドが主流だったかもしれないが、幾田氏は「新しく建てて壊すという方法ではない形を、これから発展していきたい」と未来を見据えた。その眼差しは、以前は当たり前でなかった「女性の参政権」を当たり前にある社会にした市川氏と同じ方向を向いているのだろう。“当たり前”と思っていたことがそうでないとわかった瞬間、私たちの意識と存在は普通を超えて素晴らしいものとなることを教えていただいた。
イラストレーターでCMプランナーの小田桐昭氏は、「そもそも人間は不可解で、不思議な心の動きをする生き物であり、それを直感的に理解するためには芸術的な要素が必要である」そして、「論理だけでは人は動かないからこそ、アートという人間の不思議さが必要になる」と教えてくださった。
確かに、自分を含めてそんな不確定要素満載な存在を相手にしていれば、わかりやすく共通の認識を取りやすい数字を頼りにしたい気持ちが湧き上がってしまうが、それに対して「本質的な正しさはない」と言い切る。
「一緒に世の中をひっくり返すための企み」は、まだ見ぬ人間の暮らしをより豊かにする「お金では買えない価値」につながり、そういったメッセージが込められる広告を生み出すことこそが「必ず会社も社会も変えられるのだ」と、一点の曇りもない眼差しで語られた姿がとても印象的だった。そして、社長やクライアントの宣伝部などの肩書きや会社の枠を超え、人間の不思議さについてエモーショナルに語らい、冒険を共にできた時、人の想像を超える喜びを生み出すことができると学ばせていただいた。
日本とイタリアを股にかけて発達心理学や幼児教育を研究される関エレナ氏に至っては、人が持って生まれた能力を最大限に発揮するためには「言葉を奪わないこと」が大切であると教えてくださった。
「一人ひとりが持つ100の言葉に愛を持って向き合う」のは、言うは易く行うは難しなことのようにも感じるが、彼女の母親の姿勢とレッジョ・エミリア・アプローチが大切にする考え方からすれば、子どもと大人のそれぞれが“対等な人間”として認め合う姿勢が当たり前に根付いているからこそ、本当に“向き合う”ことができるのではないかと感じた。
「学校や社会によって99の言葉が奪われてしまう」と警鐘を鳴らすのは、年齢などの上下関係や肩書きなどのフィルターで、知らず知らずのうちに萎縮して言葉にすることを恐れてしまう部分があるからだと想像する。
自分の思うままに描くことを当たり前に許すアート活動は、不安を感じ、縮こまってしまった心を解放する。表現の自由が保たれ、対等な関係性である認識がしっかりと根付いている環境があれば、人と人が互いの言葉を認め合って影響しあい、よりよい社会を築き上げていけることを学ばせていただいた。
心を残すとは
本号にご協力いただいたみなさまからは、終始「心を途切れさせない」姿勢を感じた。それは、思いを言葉にするだけでなく、それぞれの分野で身をもって実践し続けているからなのだと感じたと同時に、私の中で「残心」の考え方と結びついた。
武道や芸道になぞらえて、企業活動が一つの道であるならば、今後益々「残心」無き活動は致命的な影響をもたらすのではないかと想像している。SDGsの一言にまとめるのでなく、私たちは十人十色の言葉を持っている。十人が自分の言葉で語り、対話し合えば、百通りの選択肢が生まれる。それらが和の心でつながり、自分の想像を超える新たな気付きとなることで、まだ見ぬ道を自分たちの手で切り拓くことができるのではないだろうか。

蛭子 彩華(えびす あやか)
一般社団法人TEKITO DESIGN Lab 代表理事
クリエイティブデザイナー
1988年群馬県前橋市生まれ。剣道四段。立教大学社会学部卒業後、IT企業に勤務。結婚を機に退職し、夫の南米チリ駐在へ帯同。帰国後の2016年、第一子出産と同時に法人を創設。現在は3児の母として、様々な社会課題にデザインとビジネスの循環の仕組みでアプローチしている。